紹介内容や役職等は、掲載時のものであり、現在のものとは異なる場合があります。個別の内容、連絡先についての問合せには応じておりません。
詳しくは、本Webサイトのトップページをご覧ください。
トップページはこちらから
高校時代の先生の話をきっかけに能に興味をもち、50歳を前にして能の教室に通い、免状をもらった方がいます。「自分自身の芸を磨きつつ、能の文化を後進に伝えていきたい」と話しています。
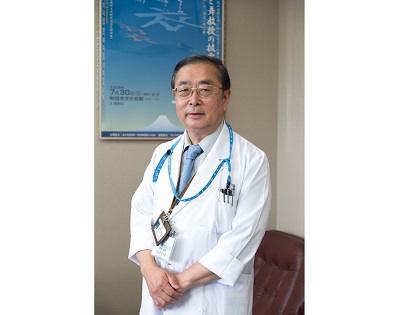
間宮 繁夫さん

『勧進帳』を独吟する間宮さん

囃子の音色とともに『羽衣・序ノ舞』を演じる
2017年7月30日、能の「謡教授」「舞教授」披露大会を開催
>能との関わりは。
「高校時代の3年間で古文を教わった先生が、プロの能楽師を目指すほど能にのめり込んでいる異色な方だったんですね。授業中、折に触れて能の話をしてくれたり、廊下を歩いているときに能の謡(うたい)をつぶやいていたりしていました。私を含めた生徒を能の舞台鑑賞に連れていってくれたこともあり、能との接点になった方です。その当時は、能の独特の動きを興味深く感じたことを覚えています。
高校卒業後は、ほとんど能と関わることはありませんでした。ただ50歳を目前にした2000年頃、日々の仕事のストレスから自分を一時的に開放したいと思うようになっていました。頭のどこかで、能の幻想的な世界に足を踏み入れたいと思っていたようです。ちょうど秋田市の広報誌で、能の流派のひとつ『喜多流』の教室情報を見かけたこともあり、その教室に通い始めました。医療の仕事と能はまったく分野が異なる領域なので、うまく切り替えができるようになり、学んできてよかったと思います」。
>披露大会について。
「2014年10月、これまでの実績と芸が認められ喜多流の『謡教授』と『舞教授』の免状をいただきました。7月30日の披露大会は、そのことを記念する機会でもありました。
謡教授では約8分間『勧進帳』を独吟し、舞教授では約25分間『羽衣・ 序ノ舞』を演じました。失敗しないようにと考えると動きが小さくなってしまいますし、頑張ろうと力むのもよくない。いままで積み重ねてきた稽古どおりにやろうとして、披露大会の当日はノーミスで演じることができました。稽古のときは厳しくやり、本番では稽古どおりにやる。雑念があると失敗するので、一番は自然体であることだと思います。ですが、なかなかそこまで到達するのは難しいですね」。
>日々の練習環境は。
「師である喜多流正教授の渡邊豊治先生に稽古をつけていただくのは、1ヵ月に3回程度。年に4回、喜多流の先生を秋田にお招きして、演技をチェックしていただく機会があります。そのほか、私を含めて渡邊先生に教わっているメンバー10人で『梅陽会』というグループを組んでおり、お互いに切磋琢磨する間柄です。自宅でも畳の上を舞台に見立てて、舞のビデオを見たり、謡の内容を歌いながら覚えるなどして、毎日練習しています」。
>今後について。
「能の世界には『謡曲十五徳』という言葉があり、能に携わることで得られる15の経験を示しています。そこには『不行而知名所(行かずして名所を知る)』や『不習而識歌道(習わずして歌道を知る)』などの経験があり、その中でも『不望而交高位(望まずして高位と交わる)』を実感します。というのも、能は『平家物語』や『源氏物語』などの古典を土台にして演目ができており、その演目の役柄に身を投じることで、昔の貴族や中国の武将などの考え方に触れられるからです。年々、そうした面白さを実感するようになりました。
2年に1度、東京で開かれる喜多流の全国大会などに参加すると、足の運びや声の出し方などで、より優れた方々がいるので身が引き締まります。その一方で、2つの分野で教授になり、周囲の見る目も変わりました。今後はその重みを感じながら、自分自身の芸を磨きつつ、能の文化を後進に伝えていきたいと思っています」。
略歴
1951年、東京都生まれ。秋田大学医学部卒。内科医。秋田大学医学部第三内科助教授、国立療養所道川病院副院長などを経て、現在は国立病院機構あきた病院院長。約18年前にプライベートで能を学び始め、2014年10月には喜多流の「謡教授」「舞教授」に。
